びおの七十二候
第31回
温風至・あつかぜいたる

温風至と書いて、あつかぜいたる、と読みます。
このあつかぜに、熱風ではなく温風をあてるところに、寒さであれ暑さであれ、微温的なこの国の気候表現があるように思います。
あつかぜというのですから、熱くて乾いた風をいうのでしょう。
この時期、よく生じるフェーン現象をいうのではないかと思います。
フェーン現象(foehn phenomena)は、風が山肌にあたって、その風が山を越えて降りてくる暖かくて乾いた風によって気温が上がることをいいます。
この名称は、ドイツの地名から付けられました。フェーンの町は、南からの熱い風がアルプスを越えて降りてくる場所に位置しました。アメリカではチヌークと呼ばれており、これはロッキー山脈を越えて吹き下ろしてくる乾いた熱い風をいいます。1943年にサウスダコタ州で起きたチヌークでは、わずか2分間で摂氏27℃も気温が上昇しました。地元の人には、猛烈な熱風によって生じたことと記憶されています。
日本での用例は、山を越えて吹き下ろされる風というより、気温の上昇として扱われています。本場のそれよりも過酷でないからでしょうか。漢字による当て字としては「風炎」という言葉があるのですが・・・。
日本の気温の最高記録は、長らく山形市の気象台で記録された40.8℃が占めていましたが(2009年時点では埼玉県熊谷市40.9℃)、この原因はフェーン現象によるものでした。
ときにフェーン現象は乾燥した強い突風を伴いますので、火災などの深刻な被害を招くことがあります。1976年に起きた山形酒田の大火はフェーン現象が原因とされます。
しかし、熱風と言っても、熱帯の砂漠地帯やインド南部のそれと比べると一時の現象的なものであって、間断なくやってくる熱風とは異なります。
スペイン・アンダルシアの村を訪ねたことがあります。その村に行って驚いたのは、道路側に向かって窓がないことでした。ほとんど白い壁で覆われていました。熱風を嫌ってのことで、建物の入り口は厚い布で覆われ、それを持ち上げて素早く室内に入るようになっていました。室内に入ると、内庭にパティオがありました。室内は薄暗くて、土地の人にとっては、その薄暗さがいいのでしょうね。
インドの熱風地帯の家の外壁は、金持ちになるほど厚くなります。そこそこの金持ちの家でも1mに達します。それは執念に近いものがあって、微温的な地域に住むものにとっては唖然とするものがあります。
日中、熱風が襲っていても、夜になるとその風も収まります。夏の星空は涼しげです。というわけで、7/7は七夕の銀河の夜です。
のきばに ゆれる
お星さま キラキラ
金銀砂子
この歌を口ずさみながら、短冊に願いごとを書きました。
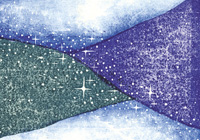 画/たかだみつみ
画/たかだみつみ
七夕の夜は、織姫と夏彦星の星逢いの夜で、大銀河を見上げます。
大銀河の夜といえば、芭蕉の
を挙げなければなりません。
日本の俳句文学の最高傑作とされる句です。
わたしは、芭蕉がこの句を詠んだとされる新潟県の出雲崎に行ったことがあります。というより、どうしても出雲崎に立ちたくて足を運びました。
出雲崎は、日本海に面した小さな町です。往来の激しい国道が通っていて、海側には「天領の里」とネーミングされた「道の駅」がある程度で他に何もありません。陸側に沿って「妻入り」の家並みが軒を連ねていて、それが約4kmも続いています。家の間口は2間か広くて3間半で、江戸時代の出雲崎町は、越後で一番人口密度が高かったといわれます。それがこの町の特徴といえばいえます。
出雲崎は、かつては佐渡金山の金の陸揚げ港として栄えました。佐渡で金が大量に産出されるようになったのは近世初頭のことです。古代・中世においては、佐渡は、伊豆・安房・常陸・隠岐・土佐と並ぶ遠流の地でした。
万葉歌人の穂積朝臣老が佐渡に流されて以降、順徳上皇・世阿弥・日蓮・日野資朝・京極為兼などが流されています。順徳上皇は、佐渡に向かう悲運を
と詠んでいます。
金山が開かれた後には、政治的流人者だけでなく、たくさんの無宿人※1が佐渡に送られました。『佐渡流人史』によれば、彼らは直接船で小木、宿根木、松ヶ崎などの港に送られ、乗船した50人のうち、35人は佐渡に着く前に亡くなったと記されています。
船を恐れた幕府役人は、江戸から奥州道、中山道を辿り、寺泊や出雲崎から佐渡に渡ったとされます。
無宿人は、戸籍がなく、働き口のない、いわばフリーターです。犯罪人ではありませんでした。彼らは、江戸に放置しておくと社会問題が発生しかねないという理由で佐渡に送られました。佐渡へは、実は罪人は送られませんでした。猛々しい罪人を管理するのは、佐渡奉行所の能力を越える、というのがその理由でした。
送られた無宿人は肉おち骨枯れ、平均寿命は3年程度だったといわれます。彼らは戸籍がないため手続き不要でした。どれだけの人が送られ、どれだけ亡くなったのか、その記録さえ残されていません。いや、記録に残してはいけない存在でした。
出雲崎は、佐渡から海を隔てて50kmの距離にあります。無宿人狩りに遭って送られたとはいえ、それを聞きつけて出雲崎にやってきた縁者は絶えなかったことでしょう。そんな話が、ここにはゴロゴロと転がっていて、自暴自棄になった者を、今度は出雲崎の役人がひっ捕らえて、獄門台※2に送ったものと思われます。
出雲崎は、要するにそういう土地でした。
芭蕉が、江戸を旅立ったのは旧暦で元禄2年3月27日(1689年5月16日)でした。門弟の曾良と共に、深川を立ち舟で墨田川を下って千住で上がりました。最初の句は、
という句でした。過ぎ行く春を惜しみ、旅に立つ別れの悲しさから、鳥や魚までが別れを悲しんでいる、という句です。
当時の旅は「野ざらし」になってもいいという覚悟あっての出立でした。殊に奥州への旅は、伊勢や善光寺への道と違って、宿所も少なく、険しいものがありました。芭蕉が月山の頂上で野宿したことが「奥の細道」に書かれていますし、馬と一緒に寝なければならなかったこともありました。それでも「漂泊の思ひやまず」と、庵をたたみ、死をも覚悟して旅に出かけたのでした。
芭蕉は、最上川の河口、酒田に比較的長く滞在しました。酒田は芭蕉にとって、よほど居心地のいい土地だったのでしょう。ようやく重い腰をあげ、芭蕉が酒田を発ったのは旧暦の6月14日でした。今の暦では7月16日にあたります。
芭蕉は、「酒田の余波日を重て、越後路の雲」を望み、温海、鼠ヶ関、中村、村上と経て、新潟へと入ります。新潟では、大工の源さん宅や風車の弥彦に泊まりました。
出雲崎に着いたのは、1689年7月4日(今の8月16日)でした。ここに来るまでの20日間、芭蕉は「暑さと湿気」に見舞われ、ずいぶん難儀を強いられました。殊に出雲崎に着くまでの数日間は雨が降り続いていました。
旅の記録は、芭蕉に同行した門人曽良の日記(『曽良旅日記』)によりますが、曽良はメモ魔で、紙製の携帯日時計を持ち歩きこと細かく記録を残しています。芭蕉一行は、この日旅籠(大崎屋)に宿泊し、曽良はこの日のことを「夜中、雨強降」と記しています。大雨の出雲崎で大銀河を見ることはできません。
ということは、芭蕉は大銀河を見ることなく、この句を詠んだことになります。つまりこの句は、芭蕉の心眼に映った天の川であって虚構です。嘘っぱちです。
それでは、芭蕉がこころのなかに天の川を描く動機や背景になったのは、何だったのでしょうか。ここからは、わたしの推理です。
出雲崎を旅する七年前、芭蕉が江戸深川の草庵時代にハレー彗星が出現し、町人に至るまで、天空への関心が高まりました。それがこの句を生んだ背景の一つだと思われます。
二つ目は、当時の旅では、天気の良い夜には野宿することがあり、満天に輝く夜空を眺めることがあり、雨の出雲崎にいて、それがふいと思い起こされたのではないかということです。
この句が発表されたのは出雲崎を発って3日後の直江津の古川市左衛門宅での句会でした。
と考えると、出雲崎で着想を得て、直江津への道中に句になったのかも知れません。
三つ目は、雨に閉じ込められた出雲崎の宿で、芭蕉は佐渡の流人とその家族の話を耳にし、それが影響しているのではないか、ということです。8月16日ということを考えると、台風が来ているわけでもないのに、出雲崎に「荒波」が打ち寄せていたのかどうか。
この句にある「荒波」とは、佐渡に流された人の落魄の海をいい、佐渡と出雲崎とを隔てる海を「荒波」と見立てて、「佐渡によこたふ天の川」を見たのではないでしょうか。
無限広大の世界を、わずか17文字で表現している芭蕉が、みんな好きなのであって、こんなふうに解読してしまうと、つまらないことになりますので、ここらで止めますが、わたしと同じように探索好きな人はいるもので、ブログを読んでいましたら、「佐渡によこたふ天の川」はあり得ない話だという指摘がありました。
その人によると、芭蕉が出雲崎に立った時期は、「天の川が佐渡に近く輝くのは朝方であり、しかも、天の川は佐渡に突き刺すように垂直に見える筈」だというのです。「天の川はいつも滝のように海に流れ込んで」おり、「天の川は、夜空から日本海に流れ込むようなかたちにしかならない」というのです。天文学者と思わしき人がそう書くのですから、多分そういうことでしょう。
芭蕉は、野宿を余儀なくされ銀河を見上げることがあったと先に書きました。寝そべって夜空を眺めると、真上の銀河は、まさに大きな川となって流れています。そのときの体験が「よこたふ」という表現になったのではないでしょうか。
芭蕉の句は、確かに虚構です。『奥の細道』は、虚実織り交ぜた紀行文であることはよく知られていることで、ほかにもおかしい句はたくさんあります。文学とは、そういうものだといえばいえますが、それは時空を超えてあるのであって、身辺的な、即物的な写生ではないのです。それを自明のこととした上で、なお探索を続けるのが愉しくていいと思います。
(『芭蕉 おくのほそ道』、萩原恭男校注、岩波文庫)
※リニューアルする前の住まいマガジンびおから再掲載しました。
(2009年07月07日の過去記事より再掲載)
※1:江戸時代において、現代の戸籍台帳、宗門人別改帳から名前を外された者のこと。ただ、必ずしもホームレス状態にあるわけではなかった。
※2:さらし首をのせるための台。

