びおの七十二候
第16回
葭始生・あしはじめてしょうず

春爛漫は、野山だけでなく、水辺にもやってきています。葦が生え始めました。
葦は「葭」とも、「蘆」とも書きます。葭始生と書いて、あしはじめてしょうずと読みます。水辺に葭が芽を吹き出しはじめる時季をいいます。
葦の新しい芽を、季語では「葦の角」といいます。地下茎から出でた芽が、まるで角のように尖っていることからつけられました。
「あし」は「悪し」にも通じていることからなのか、「善し」という別名もあります。大阪では、「難波草」 。伊勢では「浜荻」とも呼ばれています。正岡子規に
という句がありますが、この句から分かることは、子規の頭のなかに、あきらかに「難波草」という名前があったことです。まだ干潟がひろがっていた時代の大坂の水辺の様子が詠まれていて、濃い春の香りが漂ってくる句です。
やはり子規は、文句なしにいいですね。ほかにいいのは、
どれも、葦の角の光景がありありとしていて、いいですね。
さて、今候は趣向を変えて、いつもと違う話をします。
葦と聞いて、パスカルの「人間は考える葦である」という言葉を思い起こす人がいるかも知れません。何故「人間は考える葦」なのかについて考えてみます。「葦」が、弱きものの代表として人間をたとえる比喩にされていることは分かりますが、それが、何故葦なのか。すみれやバラではなくて、葦なのか、このことは中学校でこの言葉を初めて耳にしてから、ずっと疑問だったことです。
これは「後漢書」にいう、「勁草」と同じことを言っているのでは、というのが、わたしの結論です。ひしゃげそうになりながら勁さを発揮する草(「疾風知勁草=疾風ニ勁草ヲ知ル」)ですね、そういう草の代表こそ葦なのではないか、ということでした。今はそんなふうに理解しています。
平たくいうと「柔よく剛を制す」というか、「柔らかいが勝ち」というか……。
葦は、強い風が吹きつけると、しなって曲がります。風に抵抗しません。これに対して、硬い木とされる樫の木などは、風に立ち向かいます。こちらの方が男っぽいというか、勇ましいのですが、限界を超えるつよい風がくると、根っこから倒れます。
つまるところ、葦は、自らをよく知り、風に身を任せることにより自分を保持し、風が止まると身を起しては、まるで何でもなかったように、ゆらりゆらりと過ごしています。一見、頼りないけれど、しぶとくつよいのです。
なるほど人間は、自然の猛威や権力の前に弱きものです。ふだんは従順に従っているようにみえますが、それに人は屈しているわけではありません。そういう柔らかさを持てるのは、人間は「考えること」ができるからで、そういう精神のしなやかさを持つことによって人は耐えられるのだ、とパスカルはいうのです。つまり、人間の賢明さとは何かということを葦にたとえて語ったのです。そう考えると、すみれやバラではなく、比喩としては、断然、葦がいいことになります。
「人間はひとくきの葦にすぎない。自然の中で最も弱いものである。だが、それは考える葦である」
という言葉は、パスカルの『パンセPensée(思索)』に出てくる言葉ですが、しかしこの『パンセ』は、パスカルの著作ではありません。パスカルは、もっと系統的・思索的であって、片言で済ませる人ではありませんでした。『パンセ』は、パスカルのメモを元に、パスカルの弟子が断片集としてまとめ、一冊の本にしたものです。パスカルの死後、「箴言集」として出版されました。
パスカルは、40歳に亡くなりました。
パスカルは、病弱な人で、身体の苦痛とたたかいながら、思索し、研究し、実験を重ねました。パスカルは、襲って来る風に身をまかせながらも、思索する精神を持続した人であり、「人間は考える葦である」という言葉は、パスカルその人をあらわす言葉でありました。
藤
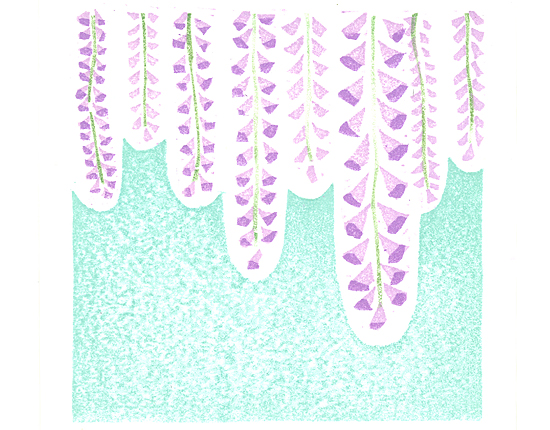
天竜川に沿って車を走らせていると、向こう岸に天竜美林が見えて、そこに藤が咲いていたりします。そんなとき、濃い緑の杉林に藤は似合う、と思います。
藤は、マメ科のつる性植物です。右巻きに、他物に巻きついて成長します。人工林の森では、樹木の上部を覆って光合成を妨げて木の成長を阻害しますので、藤のつるは嫌われ、刈り取られます。最近、日本の山林で藤の花が咲いている風景が増えてきましたが、これは山に人の手が入らなくなり、放置林が増えたからです。そうすると、杉林に藤は、風景としてはいいけれど、困ったことなのですね。
藤は、桜のあとに咲きます。
天竜川の河口近くに、推定樹齢800年といわれる熊野の長藤(磐田市行興寺)があります。開花期の藤の花房は長さ1m以上もあって、それはそれは艶やかなものです。藤棚の下にいると、幾重にも花と花が重なって、そこにいると体が藤に包まれるような感覚におそわれます。
栃木足利の「迫間の藤」は聞いた話では、熊野の長藤より凄いらしいですね。枝が畳1200枚分に広がっているそうで、藤の房がずっと遠くまで続いていて、それは日本最大のものだということでした。一度見たいと思っていますが、桜と同じで、タイミングが合わないと見られません。
清少納言は、『枕草子』に「藤の花は、しなひ長く、色濃く咲きたる、いとめでたし」と書いていて、紫式部は『源氏物語』の花宴の巻で、光源氏が藤の宴で朧月夜の君とし、明石の巻では、明石の君を「藤の花とやいふべからん」とよびます。そうしてみると、最近は藤が軽んじられているように思われます。
藤というと、日本舞踊の藤娘が思い出されます。六代目尾上菊五郎が藤の精が娘姿で踊ったことから、人気の歌舞伎舞踊の一つになっていて、当代では、坂東玉三郎の舞が有名です。俳句を4句、紹介しておきます。
(2009年04月20日・2011年04月20日の過去記事より再掲載)
